なんかどっかの人がみたら怒られそうなことばっか書いてるのでぼやかしながら書いてます。これはフィクションです。これはフィクションです。
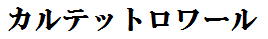

凍えた手先を温めるために吐いた息が、白い靄になって、鼠色の空へ消えていく。
笑顔、楽しそうな談笑、煌めく『降誕祭』の飾りつけ――輝く街の中を横目に、彼はまるで自分の居場所などないのだというように顔を伏せ、寒風吹き抜ける路地裏を歩いた。
胸糞悪い。
大体、なにがおめでたくてこんな行事があるのか、理解できない。ただ騒ぎたい人間が、それらしい理由をつけて催した祭事ではないのかと思いたくなる。
そもそも『誕生』というのはそんなにおめでたいことなのだろうか。今回の行事で祝うべき主賓は人間ではないが――多くの人々が家族や友人の誕生を祝い、そして自分の誕生を祝われることを望んでいる。こんな腐った世界に産み落とされることこそ、呪うべきことなのではないか。
我々に恵みを与え幸福を与えるものが神ならば、なぜ神は、その素晴らしい楽園ではなくこの地上に我々を産むのか。と、そこらへんにいる奴に聞いてみたくなったが、不信心だとか、我々は罪深い生き物で〜とか、貴方もお祈りを〜とか、そう狂気じみた目で言われるのが容易に想像できて、マルクは独り頭(かぶり)を振った。
「まーたヘンなこと考えてぇ〜」
「……ラルム」
その名を呼ぶと、彼女は猫を思わせる妖しげな笑みを浮かべた。赤みがかった長い髪は頭の両側で高く結われ、それらは複雑に波打ち幾つも重なるリボンの束のようである。ふくよかな胸、細い腰、覆うのは真紅のドレス。燃え上がる炎のような装いの彼女であるが、人の少ない路地裏で誰の目にも留まらず、すれ違いざまに振り向く人間がいないのは、全体に影をまとっているからか――否、彼女自身が影であるからか……。
「……勝手に心の中を読むな」
「あらぁ、読んだんじゃないってば。ねぇ、パッセ?」
ラルムが笑いながら目を向けた先に、狡猾な笑みを浮かべる少年。彼女の言葉を肯定するように、その顔には少し大きく見えるモノクルが右目に光る。指先が僅かに出るくらいの白衣を纏い、二人より狭い歩幅でついて行くのに懸命そうな姿は、まるで父親の真似をして遊ぶ子どものようである。
「そうとも。ボクらはアンタの心を読んだわけじゃない。超能力者じゃないからな」
「……よく言う……化け物が」
マルクの言葉に、少年の顔がむっと不服そうな表情に変わった。早足で二人を避けるマルクはそれに気付いているのか、いないのか。ぱたぱたと石畳を蹴りパッセはマルクの影を追う。嘲笑を浮かべた彼のモノクルについた、金色の鎖がさりっ、と冷たい音をたてた。
「おいおい、化け物だってよ。自己紹介もいいとこだな」
「……なんとでも言え」
「キミは……ドゥのことも、ばけもの、だって言うの……?」
細い声。
マルクは足を止め、眼前に佇む少年の姿を認めると溜め息を吐いた。
少年が首を傾げると、右側だけ長く伸びた髪がさらりと流れた。鼻先の辺りまである前髪の奥に空いた二つの虚空は、どこを見ているのかわからない。加えてそれは忙しなく泳ぎ、常に不安定な心情をこちらに訴える。彼はマルクの顔をちらと見てすぐに視線を逸らし、全身を覆う真っ黒なローブを体に巻きつけるように強く引き寄せた。
「……そこを退け、ドゥルール」
「…………やだ」
マルクはドゥルールの答えを待ってから、歩きだした。彼を押しのけるように横を通ると、悲しげな顔をしてドゥルールがついてくる。
「ねぇ、ドゥたちがばけものって、ほんとに、思ってる……?」
「さぁ、どうだろうな」
とりあえず、家に帰ろう。こんな寒い路地裏で馬鹿なお喋りをしていては、自分が風邪を引いてしまう。マルクは冷たくなった鼻を撫で、舌打ちをした。両手をコートのポケットに突っ込み、さらに早足で歩き出す。
「そうですね、馬鹿なお喋りは、お部屋で致しましょう。私がいれた紅茶などお共に」
「…………レーヴか……」
傍らで、低い男の声がした。マルクはゆっくりと男を仰ぎ見る。整えられた清潔そうな黒髪。冷たくも暖かくも見える瞳をマルクに向け、紳士的な笑みを貼り付けた彼は、的確にマルクに歩調を合わせてくる。黒い燕尾服に映える白い手袋、それをはめた左手が胸の上に置かれ、忠誠を誓う。
「いかがなされました?」
「……いちいち心を読むな、口に出すな」
「承知致しました。ですが、初めのご命令には従い兼ねます。我々は貴方の心を読んでいるわけではありませんので」
深く礼をした後、レーヴは目を細め、主人の言葉を丁寧に否定した。マルクは至極不快そうな感情を顔面に滲ませ、ひたすらに前を向いて歩くことを心がけた。
そして、どうせ家に帰っても同じなのだということを脳裏に巡らせ、立ち止まる。
背中に視線。八つ。嘲笑う奴らの表情が、そして、揃いも揃って同じ紫の瞳が、ありありと浮かんでくる。
「そう、アタシたちは、心を読んでいるわけじゃない」
「なぜなら、ボクらは、アンタだから」
「……キミの思いは、ドゥたちの、思い」
「我々は、化け物。そして、貴方も――」
四つの声が、四つの台詞を囁く。
どこへ行っても付き纏う、耳をふさいでも頭蓋に響く、彼らは、影――自身が存在する限りまとわりつく、影……。
「……うるさい!」
その瞬間。
鉛のように重たげな空に、鮮やかな炎が立ち上る。恨みを、呪いを、絶望を込めたような黒い炎――マルクの体から、その全身を包むように火柱が立った。
顔を強ばらせ、炎に任せて髪が逆立つ。黒紫色の瞳は、眼前で嘲笑う自分の分身への怒りで燃えていた。
くすくすと様々な音色の笑い声が響く。
「ごめんね、マルク。あんまりマルクが寂しそうにしてたから〜」
「そうそう、坊っちゃんがひとりぼっちで広場なんかに行くからさ」
「買い物、終わって……帰れば、いいのに……」
「つい、ですね。お独りで絶望なさっておりましたので」
――ごちそうさま。
ラルムがなだめるようにマルクの肩に手を置いた。乱れた呼吸を整えようと胸に手をかざし、目を伏せると、マルクの炎は次第に小さくなる。
「人が少ないとはいえ、こんな所で炎を出すなんて……いけませんよ、マルク様――」
マルクは四人に舌打ちした。
ある時目覚めると、このパリという街にマルクはいた。
見知らぬ景色、見知らぬ人、家族でさえ、それが自分のものであるのか――そんな折、突然現れたこの不思議な四人組に、真実を告げられる。マルクは、異世界から来た人間であると。そして、この世界のマルクと交代する形で飛ばされてきたのだと。
異世界に生まれ、『魔法』を持つマルクの力によって具現化されたのが彼らであり、彼らは絶望を糧にして生きるマルクの亡霊であるという。何のことやら分からないまま、ある出来事に巻き込まれ、マルクは四人に助けられることとなる――というのはまた別の話で、かくしてマルクは、この四人との奇妙な同居生活を強いられていた。
ここでの生活も慣れ、周囲の目を誤魔化すためにつけた記憶喪失という厄介な設定を除けば、まぁまぁ平和に暮らしている。一芸に秀でた者が通う名門、プティローサ学園では変人と言われていじめら……敬遠されているが、著名な作家、サンファール氏の孫、マルク・ド・サンファールとして快適に生活している。
サンファール氏が親族との折り合いが悪いために、逃亡者のような……もとい、謙虚な生活をしているというのには驚かされたが、頑固ながら賢英たる老人と共に暮らせることに満足していた。大作家たる彼の恩恵に与り、金銭に困ることもない。彼の遺産を狙う親族連中の影に辟易しながら、ではあるが。
――ここは十九世紀末フランス、パリ……らしい。人間の適応能力というのは素晴らしい。色々と厄介事はあるが、暮らしていけないこともない。いや、実のところ、元いた世界とそう大差ない街並みや文化だったからだと思う。不思議なことに、よく似ていたのだ、この世界と、あちらの世界は。
(どうしたのよ、マルク)
(家に……帰らないの……)
マルクの叱責によってか、蝋燭の火が消えるように彼の中へ姿を消した彼らは、内側から囁く。
マルクは彼らの声に反応せず、とある百貨店の前に立っていた。さて、どうしたものか。
少なからず、ノエルの雰囲気だけでも味わいたいという気持ちがあったのかもしれない。祖父が急用で不在、友人もいない、孤独なノエルは身にしみる……。
「勝手な想像をするなよ、化け物どもが」
(貴方の思いを感じ取っただけですので)
(せいぜい楽しめばいーじゃねーか、坊っちゃん)
我々もお供致します、というレーヴの言葉に胸のつかえがとれた気がした。
適当にぶらつこうかと人混みの中へ一歩踏み出した時だった。
「ぼくじゃない!」
まだ細く、幼い少年の声だった。
声のした方へ目を向けると、百貨店の中に構えた店の一つ、その入口と思しき場所で太った男と少年が何やら口論をしている。
太った男は真っ赤な顔で少年の小さな右手を掴んでいた。少年の手は固く丸め込まれていて、よほど強く握り締めているのか、骨が浮き出ていた。
「たった今! ここで! 盗んだだろ!」
「そんなことしてない!」
なるほど。
少年が疑われるのも無理はない、とマルクは少年の容貌に目を向けた。
皮脂でべたついているように見える髪、所々黒く汚れた顔。薄いコートを羽織り、その下にはぼろ布のようなシャツ、擦り切れた靴、そして身に付けているそのどれもが彼の体には大きくみえた。どこからか拾ってきた、そう推測させるには十分だった。
(……マルク?)
ドゥの心配そうな声が響いた。
それでもマルクは、その浮浪児と男の会話を聞き続けた。やめとけよ、というパッセの声も聞こえた気がした。
「やってない? ……だったら、その手ン中見せて見ろっつってんだろ!」
男の顔が更に赤く染まる。怒りに我を忘れ、こめかみに血管が浮いていた。
振りかざされた男の拳に、少年はたじろいだ。
その瞬間、シャツの間から少年の首にキラリと何かが光ったのが見えた。
「――待ってくれ」
マルクは、男に声をかけた。
二人分、いや、通行人の分も含めれば相当な数の瞳が彼を見ていた。
少年の右手から商品――小さな指輪を奪うと、男に差し出した。
「俺が頼んだんだ。持っておいてくれと」
俺が急に居なくなったから、店を飛び出してしまったんだろう。そう言いながら、瞳は少年に向ける。大人しく話を合わせろ。
男が何事か言い出す前にマルクは金を差し出す。指輪の値段など知るはずもないが、かなり色をつけたつもりだ。
満足したのか、男は金を受け取ると感情もなく、どうも、と言った。
マルクは少年の手を引いてそこから足早に立ち去った。人目につかない場所へ来る間、少年は随分と子どもらしくない、妙に冷たい表情をしていた。
「離せよ」
少年がマルクの手を振り払う。
店と店の間の、従業員だけが通るような空間に来ると、少年の雰囲気がより粗野なものになった気がした。
いまにも噛み付いてきそうなその獣を押さえつけ、暴れる彼の首から首輪を奪う。
首輪――彼が盗んだ、十字架の首飾りを。
「これを盗むためにわざとあの指輪を盗んだ。そうだろ」
少年の瞳が一瞬揺らいだように見えたが、彼はマルクを見据えたままだった。
マルクは続けた。
「間違えたとでも言って指輪は返せばいい。店主の注意はそこにいったまま、お前は店を出られる。それに、もし十字架のネックレスを盗んだことがばれても気にする必要はなかった。信徒なら常に持ち歩いていても不審に思われない。だから、あえて、十字架を選んだ。ましてや今日は降誕祭。店主もそりゃ疑わない」
マルクは、そうだろう、と締めくくった。
少年が目を伏せる。小さな体は震えているように見えた。
「――だったら、何だって言うんだよ」
小さな、絞り出すような声だった。
行き交う人々の影がちらちらと光を遮り、少年の表情をさらに不明確にしている。
ふと、彼の薄い胸板の辺りに目をやる。その奥、さらに、奥、彼の胸の内を“見る”と、そこには、赤黒い炎が燃えていた。
「お前なんかに、分かるかよ。金持ちに――人間に、ドブネズミのことが分かるのかよ!?」
吐き捨てるように少年は言った。
そして、驚愕するマルクの手からあの指輪と十字架の首飾りを取ると、通りに飛び出していった。慌てて彼の姿を探したが、人波のせいで走馬灯のように変化する景色に、もはやそれも叶わなかった。
店員らしき人物に見られていたのか、大丈
夫ですか、ムシューと声を掛けられたが、それに答える気力も無かった。
少年の姿を思い返しながら、自らの格好に目を向ける。白いシャツには染みもしわも無い。ぴかぴかの革靴、ヴェルヴェットのコート――祖父にあつらえてもらったものは、どれも一級品のオートクチュール……。
ショーウインドウに映った自分の姿は、傍目には、資本家階級(ブルジョワジー)そのものであった。
A suivre...
.